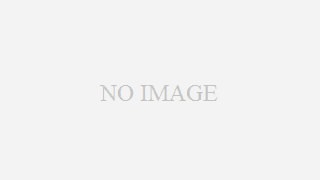 未分類
未分類 社会保障制度が抱える構造的ジレンマ
社会保障制度が抱える構造的ジレンマ個人間の援助と制度化された社会保障では、関係性の性質が根本的に異なり、それぞれ固有の問題を生むという点を、いくつかの角度から考察してみます。関係性の変質:「顔の見える援助」から「匿名の権利」へ個人が困窮者を...
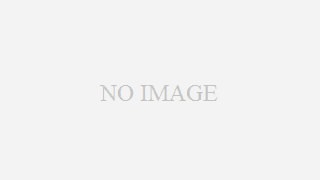 未分類
未分類 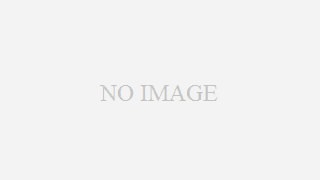 未分類
未分類 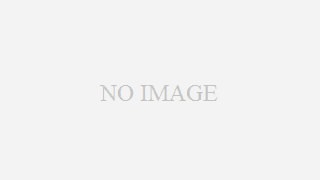 未分類
未分類 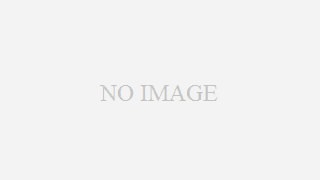 未分類
未分類 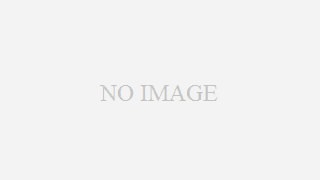 未分類
未分類 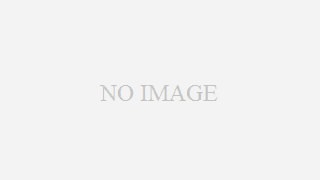 未分類
未分類 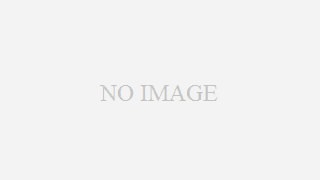 未分類
未分類 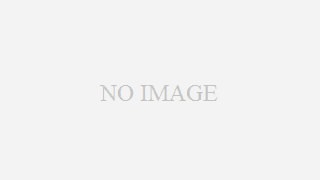 未分類
未分類 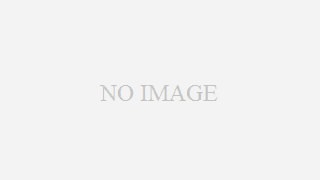 未分類
未分類 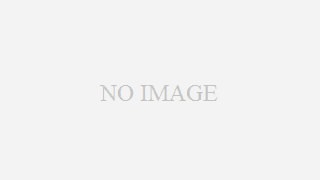 未分類
未分類